みなさん、こんにちは。
緩和ケア科所属医師のYuukiです。
最近肌寒くなってきて、赤ちゃんの服装や寝床の調整が必要になってきました。
先日投稿した「育休ブログ前編」では多くの方から好意的な反応を頂き、非常に嬉しく思います!
特に女性の方から「夫に見せます!」という反応が多かったです。
さて今回は、前回の育休ブログの後編をお送りします。
実際の育休内容とその気づきを紹介していきますので、これからの方は参考にされてみてください。
退院 そして育児生活へ
ついに退院日を迎えました。
母親に手伝ってもらいながら問題なくいけるはず…
でしたが、チャイルドシートの使い方が分からなくなるトラブル発生!
みんな汗だくになりながら説明書やスマホを見て、なんとか解決!
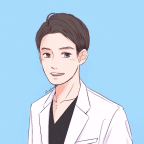
暑い中泣かずに眠ったまま待ってくれていました。偉かったね!
- シフト制の導入
トラブルもありながら育児生活がスタートしたわけですが、予め妻と相談し、シフト制にすることを決めていました。

初日は、妻と2人で泣いた時の対応を一緒に確認しながら行い、2日目には自分1人でも対応できるようになったので、すぐに導入しました。
大まかにはこのスケジュールで動いていましたが、毎日話し合いながら時間は修正しました。
自分の大きな役割は毎日の沐浴でした。お風呂が好きなようで、いつも機嫌良く入ってくれました。

その他に、オムツ交換やミルク作りとミルク授乳・瓶の消毒などは、気づいたときにはなるべく自分が行うようにしました。
睡眠時間に関しては7時間確保されているため、私は十分休むことができました。
しかし妻は3−4時間に1回は起きて授乳か搾乳する必要があり、私ほど満足には休息出来ていない様子で、申し訳ない気持ちでした。
ところで、夜泣きの対応を「夜勤」と表現することが多いですが、正しくは「超過勤務」ですね。
- 意思疎通が取れない相手の対応
赤ちゃんは言葉を話せず、視力は未発達で、聴力はあっても言葉はまだ理解できません。
そんな相手の対応をするのは、認知症患者さんを対応するのにどこか似ているなと感じました。
認知症患者さんを対応する際に役に立つ「ユマニチュード」という考え方があります。
簡単に説明すると、意思疎通が取れないからといって、声かけもせずにケアを行うのではなく、きちんと目線を合わせて『今から〇〇しますよ〜』と声かけをしながらケアを行うことです。
この際には、「肌の触れ方」や「声かけの仕方」などにもポイントがあり、自分も日頃の診療で出来るだけ意識して行うようにしておりました。
この考え方は赤ちゃんのお世話にも活用できるなと感じていて、
•目線を合わせる(視界のないところから急に掴まない)
•動作することを声に出す(今から〇〇しますよ〜)
•着地するように触れる(いきなりギュッと掴まない)
などを意識すると、泣くことも比較的少なく感じます。
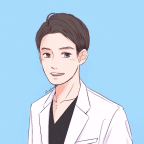
日頃の診療の知識が育児に活きました!
赤ちゃんの尊厳も大事にしたいですね!
以下の書籍はとても読みやすく、医療従事者だけでなくご家族で介護されている方にもおススメです。
- レスパイトケアの重要性
妻は産後の身体状態が回復していない中、頻回な母乳育児に伴う睡眠不足で四六時中ずっと一緒にいると、頭痛などの身体症状や疲労感が出ている様子が感じ取れました。
そこでレスパイトケアが必要と考え、産後初めて1人で出かけてもらいました。
ランチを食べ、買い物をし、リフレッシュした様子で帰ってきました。
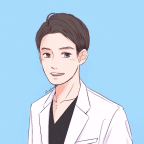
お母さんの休息も大切ですね。
今回は短時間でしたが、妻の様子を見て、今後もこのような時間を作っていきたいと思いました。
今回のことで、産後のレスパイトケアについて少し調べてみました。
このコロナ禍での出産・育児を経験した人の産後うつの割合は増加し、産後のレスパイトケアの重要性は高まっているようです。
現在は、産後ケアホテルなどレスパイトケアとして利用できる施設も少しずつ増えてきています。
実際にレスパイトケアのため産後ケアホテルに泊まった人の感想はこちら
料金はまだまだ高く、九州にはまだありません。
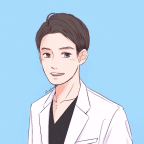
家族一緒に泊まれるところが安心ですね!
九州にも早くできて欲しいです。
- 育休制度
9月19日は、育休を考える日だそうです。
育休期間中の自分にとってはタイムリーな情報でした。
実際にその期間に多くの企業がSNSで育休について取り上げていました。
特に積水ハウスのYouTubeの動画が興味深いです。
育児休暇に対するイメージと実際に育児休暇をとった人の意識等について、アンケートやヒアリングした内容が含まれています。
まだまだ育休を取得する父親は少ないですが、育休を取ることにより、復帰した仕事へのモチベーションに繋がる相乗効果や、育休から復帰した人がもたらす周りの人の意識の変化からも会社へのメリットがありそうです。
2022年10月1日から新制度「産後パパ育休(出生時育児休業)」もスタートします。
この制度がスタートすることで、母親が産後の心身共に辛い時期である産後8週間の間に4週間の産後パパ育休を取得し(2回に分割して取得することも可能)、通常の育休も産後1年の間のどこかで育児休暇も取得することができます。
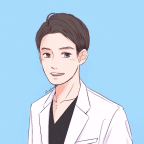
育児休暇によって社会全体が明るくなれば良いですね。
- 育休最終日
最終日はちょうど「初宮参り」に当たるため、飯塚市の神社にお参りに行ってきました。
健やかに育ってくれることをお祈りし、心身共に晴れやかな気分となりました。
これからも仕事に育児に頑張れそうです!

妻の育児休暇の感想
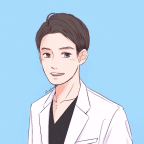
妻から育休の感想を頂きました!
夫から育児休暇の話を聞いた時、まず育児休暇を取得できる環境であることに驚きました。育休をとることにはなりましたが、なんとなく1人でもお世話できるだろうと妊娠中は考えていました。
しかし、産後入院中からその考えは甘かったと痛感しました。入院中は面会禁止で、個室で赤ちゃんと2人っきりの母児同室。体力もなく、身体も思ったように動かせないという現実や頻回授乳に伴う睡眠不足も続きました。孤独でどんどん心身共に疲弊していくのがわかりました。
自宅に帰って、育児休暇の夫との生活が始まり、大人が2人いて育児が分担できることがこんなにありがたいことなのだと感じました。夫はオムツ交換やミルク授乳、沐浴、爪切り、寝かしつけなど、ほとんどのお世話ができるようになっていました。
夜間もシフト制で担当することで、心身共に回復ができ、また任せられることで、とても頼りになりました。子供の可愛かった一面や大変だったことを話し、分かち合える同志のように感じていました。
何よりも子供の成長を一緒に共有できた1ヶ月の育休の時間が、家族3人で新たな家族の形として、良いスタートが切れたように感じ、嬉しかったです。育休が終わった今も、仕事終わりに子供にかけ寄る姿やお風呂に積極的にいれる姿に父性を感じますし、子供も夫に対し、安心感を抱いているように見えます。
育児休暇を取得してくれた夫にも感謝してますし、育児休暇を取得できるよう調整してくださった職場の方々にも感謝しかありません。本当にありがとうございました。
これからも育児は続いていく
育児休暇を終了し職場に復帰したわけですが、これまで通りの分担は不可能で、妻には大きな負担をかけることになります。
それでも自分に出来ることを見つけながらお互いに助け合い、体調に合わせてスケジュールを変えながら日々を過ごしています。
これからも育児は続きますが、大切なのは無理をし過ぎないこと!
支え合いながら過ごしていきたいです。
感謝の言葉
このような大変貴重な時間を調整してくださった職場の皆様には、感謝の思いでいっぱいです。
家族の中で一生思い出に残る時間が過ごせましたし、3人のいいスタートになったと思います。
自分が育児休暇を取得したことが周囲に良い影響を与えられるよう、これからも頑張っていきたいです。
また、時折手伝いに来てくださったご両親にも感謝を伝えたいです。
2人だけでは難しい場面もあって、それをスケジュールを合わせて助けて頂き、本当にありがとうございました。
スタッフ募集中!
飯塚病院 連携医療・緩和ケア科は2023年度の内科専攻医・後期研修医・スタッフ医師を募集しています!現在は新型コロナウイルス第7波の渦中にあり、大変な日々をお過ごしのことと思いますが、オンラインでの就職面談や病院紹介も承っております。
ぜひお気軽にお申し込みください!!
見学のお申し込み方法について
オンライン面談について
- 緩和ケアの研修や当院での勤務にご関心があっても、こういった社会状況では見学が難しいという方もいらっしゃると思います。
- そこでオンラインでの情報交換やご質問へのご回答もおこなっております。
- 個別に勤務の様子や研修内容、具体的な雇用契約内容などについて30分−60分程度、お話しさせていただきます。
- 以下のフォームより、オンライン面談の希望とご記載いただきご送信ください。
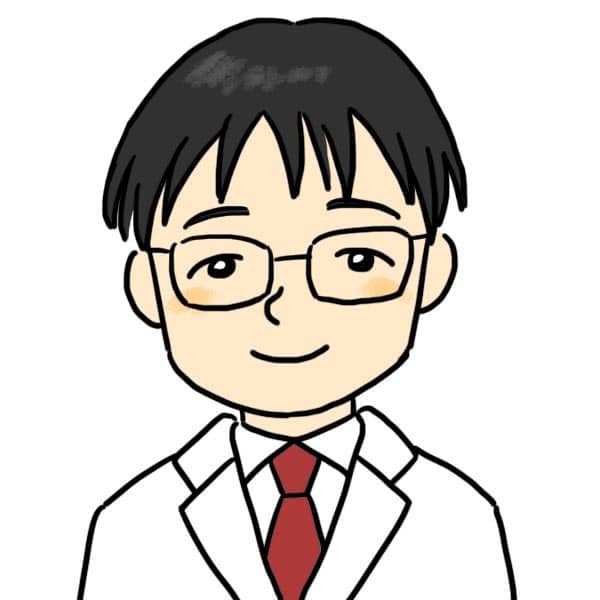
みなさまと一緒に働ける日を楽しみにしています!


